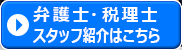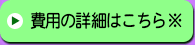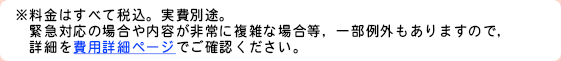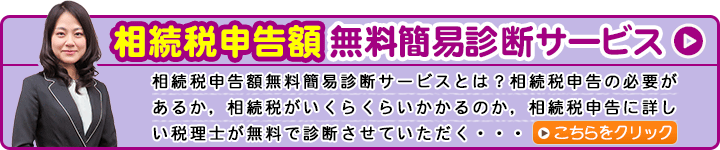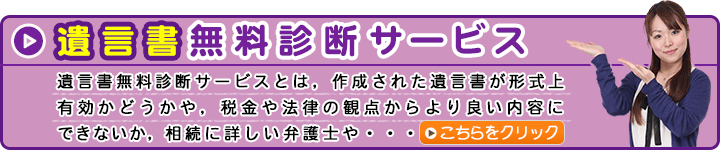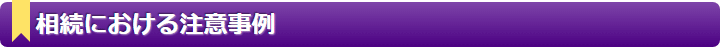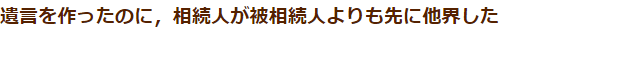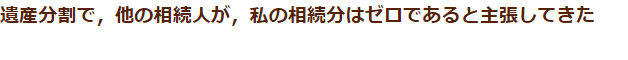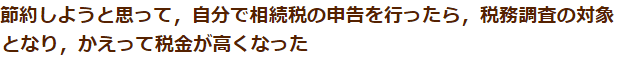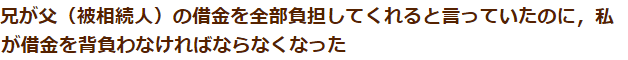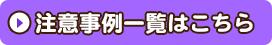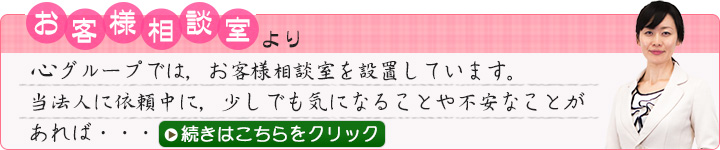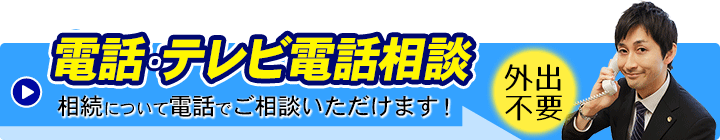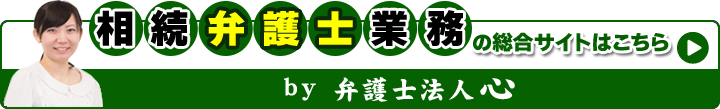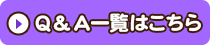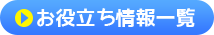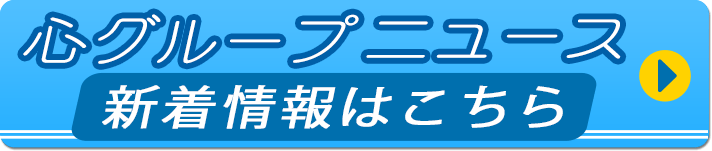業務内容
選ばれる理由
- 1大阪エリアの相続案件を集中的に取扱う相続チームの弁護士・税理士が担当詳しくはこちら
-
私たちは、相続を扱う弁護士・税理士が相続案件を集中的に取り扱っています。
これは、一人の専門家があらゆる分野を広く取り扱うよりも、取扱分野を絞り、それを集中的に取り扱う方が、圧倒的に多くの経験を積むことができ、クオリティの高い業務を提供することができるからです。
閉じる - 2相続をワンストップで解決詳しくはこちら
-
相続では、一般的に、遺産分割の交渉や裁判は弁護士、相続税は税理士、不動産の相続登記は弁護士あるいは司法書士、預金解約などの相続手続きは弁護士、司法書士あるいは行政書士といったように、多くの専門家が関与しますが、それぞれ別々の事務所の専門家に相談・依頼するのはとても大変です。
私たちは、グループ企業の弁護士・税理士が連携してワンストップで対応することで、ご依頼者の方のご負担を最小限にいたします。
閉じる - 3法律・税金の両方が分かることの強み詳しくはこちら
-
遺言書作成や遺産分割などは、法律に詳しいだけでは不十分で、税金に関する深い知識が必要です。
なぜなら、誰がどの遺産を取得するか否かによって、相続税額が大きく変わってくるためです。
例えば、「小規模宅地等の特例」を活用することで、不動産の評価額を最大で8割減にすることができ、また、「配偶者の税額軽減特例」を活用することで、取得する相続財産のうち1億6000万円までか、法定相続分が1億6000万円よりも多い場合は法定相続分まで、相続税がかからなくなります。
税金に関する知識が十分でない専門家に依頼してしまうと、法律的には正しかったとしても、過大な税金を支払うことになりかねません。
私たちは、相続分野に詳しい弁護士・税理士が常に連携して対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
閉じる - 4担当者とは独立したお客様相談室を設置詳しくはこちら
-
案件の担当弁護士・税理士やスタッフから独立した機関として「お客様相談室」を設置し、ご依頼中に担当者に伝えづらいようなことがあっても、安心してお客様相談室にご相談いただけるような体制を整えております。
また、お客様にアンケートをお送りし、改善を実施するなど、ただ案件を解決するだけでなく、お気持ちの部分でもご満足いただけることを徹底的に追求しております。
詳しくはこちらをご覧ください。
閉じる - 5大阪駅5分・北新地駅1分でアクセス良好、駐車券サービス有り詳しくはこちら
-
お客様の利便性を優先し、大阪駅の近くで、かつ、場所もわかりやすい「大阪駅前第3ビル」の30Fに事務所を設置しています。
事務所の近くにはたくさん駐車場がありますので、お車でお越しいただくこともできます。
有料相談のお客様・ご契約いただいたお客様には、指定駐車場の料金をサービスさせていただいております。
相続分野では、資料を直接見ながら話した方がわかりやすいということも多く、事務所にアクセスしやすいことが私たちの強みの一つです。
閉じる
Q&A
大阪で相続について相談したいのですが、誰に相談すべきですか?
回答はこちら相続に法的判断や相続人間の調整が必要な場合は、弁護士に相談するのが一般的です。
相続税の申告や財産評価が関係する場合は、税理士との連携が重要になります。
大阪には相続を取り扱う専門家が多くいますが、取扱分野や他士業との連携体制は事務所ごとに異なります。
そのため、相談前に対応範囲や連携の有無を確認することが重要です。
争いのない相続についても相談できますか?
回答はこちらはい、争いのない相続についてもご相談いただけます。
遺産分割協議書の作成や相続登記、預貯金の解約など、相続手続きをまとめてサポートします。
相続手続きとは何をすればいいのですか?
回答はこちら相続手続きとは、遺産分割協議書の作成、預貯金・証券口座の解約、不動産の相続登記や自動車の名義変更などを行う手続きです。
これらの中には手間や専門知識を要するものも多く、大阪法務局などの役所に出向く必要がある場合もあります。
そのため、相続手続きは専門家に相談・依頼することが有効です。
事務所に行かなくても電話やオンラインで相談できますか?
回答はこちらはい、電話やオンラインでの相談にも対応しています。
オンライン相談では、画面共有を使って資料を確認しながら相談することも可能です。
どのタイミングで相談するのがよいですか?
回答はこちら相続が発生したら、できるだけ早い段階で相談することが望ましいです。
相続手続きには期限が定められているものもあり、状況によっては不利益が生じるおそれがあります。
また、生前に将来の相続について相談することも可能です。
サイト内更新情報(Pick up)
2025年12月9日
相続税
相続税の計算方法
まずは、遺産の総額から相続税の総額を計算します。そのうえで、各相続人が取得する遺産の額に応じて、各相続人が支払うべき税金を計算します。このような言葉だけの説明では・・・
続きはこちら
2025年11月12日
遺言
遺言とエンディングノートは何が違うのか
遺言という制度自体は、かなり昔から知られています。一方、近年の終活ブームの中で、「エンディングノート」の認知度が高まってきています。エンディングノートとは、自分が・・・
続きはこちら
2025年10月24日
遺言
遺言書の効力
「遺言書に書いて効力が発生すること」は、法律で限定されています。仮に「遺言書に書いて効力が発生すること」以外のことを書いた場合でも、遺言書自体が無効になるわけでは・・・
続きはこちら
2025年9月29日
手続き
株式の名義変更手続き
株式も遺産の一部なので、相続財産の中に株式がある場合は、名義変更の手続きを行う必要があります。一言で株式と言っても、大きく分けて上場株式と非上場株式の2つの種類が・・・
続きはこちら
2025年8月28日
遺留分
遺留分を減らす方法
特定の相続人に多くの財産を相続させたいと思うきっかけは様々あると考えられます。例えば、事業を営んでいる方であれば、事業を継ぐ相続人に事業用の財産や株式を相続して・・・
続きはこちら
2025年6月19日
遺産分割
遺産分割をする際の流れ
まずは相続財産を調査して、遺産の全容を把握する必要があります。相続財産調査をどれだけ丁寧に行えるかによって、取得できる遺産の額が大きく変わるケースもあります・・・
続きはこちら
2025年4月11日
相続税
不動産の相続の手続き
相続税の基礎控除とは端的に説明すると、「一定額の遺産があっても、相続税を発生させない枠」のことです。相続税は、亡くなった方が残した遺産に対して課せられる税金です。しかし・・
続きはこちら
大阪で相続に取り組む想い
1 大阪で相続問題に向き合う弁護士として

私は、当事務所の所長を務めている大澤耕平です。
大阪で生まれ育ち、弁護士・税理士としても、大阪を拠点に業務を行っています。
弁護士となった後も、生まれ育った大阪の地に貢献したいという想いから、相続分野を中心として事務所を運営してきました。
大阪の方は、ご家族や親族とのつながりを大切にされ、率直にお気持ちや考えをお話しされる方が多いと感じています。
私は、そのような大阪の皆様のお話を丁寧に伺い、それぞれの事情や想いを正確に理解したうえで、相続に関する問題に向き合うことを大切にしています。
相続は、財産の問題であると同時に、これまでのご家族の関係性や感情が強く表れる分野です。
だからこそ、一人ひとりのお話にしっかりと耳を傾け、納得いただける解決を目指したいと考えています。
2 大阪の相続事情を踏まえた私の基本姿勢
相続では、親族間で意見が対立し、争いに発展してしまうことが少なくありません。
大阪の相続案件では、「不動産が相続財産の中心となるケース」「自営業や家業の承継が問題となるケース」など、財産の分け方や評価を巡って調整が難しい事案も多く見受けられます。
私は、大阪を中心に相続案件を継続して取り扱う中で、法的な知識だけでなく、当事者同士の感情や利害を踏まえた調整の重要性を強く感じてきました。
相続の結果だけでなく、その後の親族関係にも配慮した解決を目指すことが、相続に携わる専門家として重要だと考えています。
また、相続に関する法律や制度は、法改正等により頻繁に変更されます。
そのため、日々知識の更新を行い、常に最新の情報に基づいた助言ができるよう、研鑽を重ねています。
3 大阪の相続についてお気軽にご相談ください
相続は、事前に備えておくことで、防ぐことのできるトラブルも多くあります。
私自身も、将来に備えて遺言を作成し、財産関係を整理したうえで、家族に伝えています。
相続は特別な方だけの問題ではなく、誰にとっても身近なものだと考えているからです。
大阪で相続についてお悩みの方はもちろん、将来に向けて早めに準備を進めたいという場合も、どうぞお気軽にご相談ください。
相続で各専門家が協力できることの強み
1 相続の相談でたらい回しになることも

一言で相続と言っても、その内容はとても幅が広いため、異なる分野の専門家が協力して手続きを進めなければならないケースが多くあります。
例えば、遺産の分け方で揉めてしまった場合と、不動産の名義変更を行う場合、相続税が発生する場合とでは、それぞれ異なる分野の専門家に相談する必要があります。
このように、相続はとても多彩な分野であり、各種専門家の連携が必要不可欠です。
もし、各専門家が連携できていない事務所に相談した場合、その事務所が扱っている分野は担当してもらえるものの、他の分野については他の事務所に相談してほしいと言われるかもしれません。
すると、相続でお困りの方は、色々な分野の専門家の事務所を訪ね歩かなければならず、そのたびに相談内容を説明し直す必要が生じることになります。
2 各専門家が協力することでワンストップサービスが可能
法律の問題や税金の問題など、相続について複数の分野の専門家が連携している事務所に相談すれば、1回の相談で、すべての事情を説明することができ、同時に複数の手続きを進めていくことが可能になります。
つまり、相続でお困りの方にとっては、色々な事務所に行き、毎回同じ説明をするといった手間を省くことができます。
3 相続における見落としを防ぐことができる
相続では、様々な分野・様々な角度から解決の糸口を探す必要があります。
様々な角度から解決策を考えられていないと、例えば、法的な争いの解決に気を取られて税金面での手続きを怠り、多額の税金を支払うことになってしまったといった事態に陥るおそれがあります。
反対に、税金のことばかりに気を取られ、次の相続の場面まで想定した遺産の分け方ができなくなるような事態に陥るおそれもあります。
このように相続では、1つの分野・1つの角度から見ただけで手続きを進めてしまうと、後々トラブルが発生することがあります。
法律面や税金面など、多面的な検討が必要となる場面では、異なる分野の専門家に相談して、異なる角度からベストな解決策を考えることが大切です。
4 相続のワンストップサービスをご提供します
私たちは、複数の分野の専門家が協力して、相続のワンストップサービスを実現しています。
幅広い相続のお悩みに対応しておりますので、相続でお悩みの方は、ぜひお問い合わせください。
相続の相談は、相続に強い専門家に
1 法律の世界でも、その人によって得意分野があります

日本では、約2000前後の「法律」と呼ばれるものがあり、その数は年々増え続けています。
個々の「法律」の中に、第1条、第2条といった形で、条文が規定されています。
例えば、相続の場面では、主に民法という法律が使われます。
民法の中には、第1条から第1000条を超える数の条文があります。
このように、1つの法律の中でも、多くの条文があることから、全ての分野に詳しくなるのは、かなり難しいと言えるでしょう。
他方、もし1つの分野に絞って、集中的に取り組めば、その分野についてのノウハウが蓄積されていきます。
そのため、相続について相談するのであれば、相続の分野を数多く取り扱い、相続に強い専門家に相談することが大切です。
2 相続に強い専門家の見極め方
⑴ 実績を確認
まず、相続の案件をどれだけ多く扱っているかという実績を確認しましょう。
当然ながら、複数の分野の案件を浅く広く扱っている専門家より、相続の案件を集中して取り扱っている専門家の方が、相続分野において多くの実績を積んでいると言えます。
依頼者の方の中には、「ある程度年配で、ベテランの専門家がいい」とご希望される方がいらっしゃいます。
しかし、士業を20年続けているベテランであっても、年に5件しか相続の案件を扱わないのであれば、相続の案件を年に100件扱っている若手の専門家の方が、はるかに実績を積んでいると言えます。
⑵ 法律の改正について研究しているかを確認
相続の分野では、近年、大きな法改正が行われました。
法律が変われば、当然とるべき戦略も大きく変わります。
そして、相続を多く扱っている専門家であれば、法改正について相当の研究をしています。
その専門家が法律の改正に詳しいかどうかは、無料相談などの際に、「今回は改正された法律が関係してきますか?」といった質問をするとよいかと思います。
もし、相続を多く扱っており、法律の改正に詳しい専門家であれば、しっかりと説明ができるはずです。
3 税金にも詳しい専門家に相談を
相続と税金は、切っても切れない関係にあります。
遺産の分け方によっては、相続税の金額が大きく変わることもあるため、相続を扱う専門家は、税金にも詳しくなる必要があります。
さらに、相続税法に詳しくなければ、相続税を安くするための特例制度を使えるかどうかや、相続税の申告の期限などを視野に入れた戦略などを駆使することができません。
そのため、相続の相談をする場合は、法律だけでなく、税金にも詳しい専門家に相談することが大切です。
JR大阪駅から大阪オフィスへのアクセスについて
1 改札を出たら中央南口方面へ
JR大阪駅の改札を出たら「中央南口」方面の看板を目印にお進みください。
進んでいくと、エスカレーターがありますので、エスカレーターで下ってください。

2 「SOUTH GATE BUILDING」を直進
「SOUTH GATE BUILDING」を直進し、しばらく進むと、円形の広場に出ます。
「第2ビル・第3ビル・第4ビル」の看板がある方にお進みください。
3 第4ビルを左手に直進・その先の十字路も直進
しばらく進むと、左側に第4ビルが見えてきます。
第4ビルを左手に、直進してください。
進んでいくと十字路がありますので、そこも直進してください。

4 第3ビルに到着
左手に、第3ビルがあります。
30階にお越しください。

北新地駅から大阪オフィスへのアクセスについて
1 東口改札を出て右折
北新地駅の東口の改札を出て、右に曲がり、「大阪駅前第3・4ビル」の看板を目印に進みます。

2 広場に出たら左側の通路へ
広い広場に出て、最初に見える左側の通路を進んでください。
第3ビルがあります。
東梅田駅から大阪オフィスへのアクセスについて
1 南改札から出てください
東梅田駅の南改札を出て、8番9番出口の方にお進みください。


2 第4ビルに入ってください
エスカレーターを上って左に進むと、第4ビルの入り口があります。
第4ビルに入り、直進すると、第3ビルがありますので、30階にお越しください。